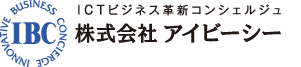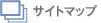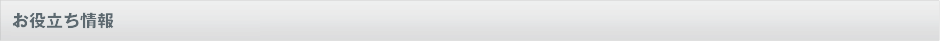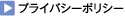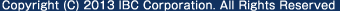使える文書コンテンツ
使える文書コンテンツ フォーマル文書のポイント
フォーマル文書のポイント ビジネス文書の書き方
ビジネス文書の書き方 時候の挨拶
時候の挨拶
■ 挨拶状・礼状(フォーマル)
フォーマルな場合は、白無地の厚めの用紙が重みがあるので好ましい。 縦書きの方が堅い印象を与え、横書きの方がやわらかい印象を与える。 前文-主文-末文-後付-別記という順序で堅い表現でまとめる。 出欠確認を行う場合は表・裏の両面を印刷し、切手を貼ったはがき又は官製はがきを同封する。 慣用句を使った丁寧な表現をすることにより先様への敬う気持ちが伝わる。
■ 挨拶状・礼状(セミフォーマル)
白無地ではなく、デザインした用紙と文例をアレンジすれば個性化や差別化ができる。 横書きの方がやわらかい印象を与えるため、セミフォーマル形式では横書きが多い。 前文-主文-末文-後付-別記というスタイルで柔らかい表現でまとめる出欠確認を行う場合は表・裏の両面を印刷し、 切手を貼ったはがき又は官製はがきを同封する。 友人などへは、フランクな会話調な表現を使用し、フレンドリーな気持ちを伝える方法もある。
■ 文書の構成(前文-主文-末文-後付-別記・添え書き)
前文は挨拶です。(頭語からはじまり時候の挨拶という順序です) 主文は相手に伝える用件です。 (さて、ところで、実は、つきましては、などの起こし言葉に続けて簡潔にまとめる部分です。) 末文は締めの挨拶で、結語で終わります。 (例:どうかお元気で、まずはお知らせまで、まずは略儀ながら書中にて、敬具など) 後付は日付、署名(差出人)、宛名などです。 (署名宛名ともに姓と名で書くようにします。姓のみ名のみは目下か親しい人のみ。) 別記は、日時、場所(住所地図や電話番号)をわかりやすくするために、記 として、列記し、 添え書きは追記や追伸など主文で書き落としたことを補足する場合に用います。 駐車場の有無や運転手さんへの気配りまで考え、 控え室有無と付記する場合など相手に来ていただく場合の返信を用いる場合に使うとよい。
■ 頭語と結語
時候の挨拶などから相手様の様子を伺い(気づかい)、自分の近況そして、お礼やお詫びなどの言葉として本文に入ります。
| 一般冒頭語(男女):拝啓 拝呈 啓上 敬白 一筆啓上 一筆拝呈 → 結語:敬具 拝具 敬白 |
| 一般冒頭語(女性):一筆申し上げます → 一結語:かしこ かしく 失礼致します ごめんくださいませ |
| 丁寧な冒頭語(男女):謹啓 謹呈 謹白 恭啓 粛啓 → 結語:謹言 再拝 |
| 丁寧な冒頭語(女性):謹んで申し上げます → 結語:かしこ |
| 前文を省略する場合(男女):前略 冠省 略啓 → 結語:早々 草々 勿々 不一 不備 不尽(目上の人には用いない |
| 前文を省略する場合(女性):前略ごめんください → 結語:かしこ(目上の人には用いない) |
| 前文省略、急ぎの冒頭語(男女):急呈 急啓 急白 火急 → 結語:草々 不一(目上の人には用いない) |
| 前文省略、急ぎの冒頭語(女性):取り急ぎ申し上げます 早速でございますが → 結語:かしこ(目上の人には用いない) |
| 返信の場合の冒頭語(男女):拝復 復啓 拝誦 → 結語:拝答 啓答 啓白 |
| 返信の場合の冒頭語(女性):お手紙拝見いたしました お手紙ありがとうございました → 結語:かしこ ご返事まで |
| 頭語を使わない場合の結語:以上 早々 草々 さようなら ごきげんよう ごめんください、 祝事の場合「めでたくかしこ」など。 |
■ 時候の挨拶
時候のあいさつは、季節感や実感を心情や近況から表現するのがこのましく、 季節の変わりめに従わないと受けた側が読んだときに、常識しらず!と疑われて恥をかくかもしれません。 春でも涼しかったり、秋の涼しい時期に暖かかったりと、気温の変化も激しかったりします。 無難な文章を使い分けるのが好ましいでしょう。
■ タイトル
行事や案内状などは「●●●●のご案内」、「●●●●のご挨拶」、 「●●●●のお知らせ」などとタイトルをつけた方が効果的。
■ その他
移転通知や独立開業などの自己都合による挨拶文中に「私こと」、「私事」、 「私儀」を用いる場合には、私こと、私事、私儀と文字を1.5~2ポイント縮小する。 これは自分がへりくだり先方様に気を配ることを意味する習わしです。
■ 書体(楷書体が基本)
本来文章は1部づつ手書きでかく方が相手に気持ちが伝わります。 印刷文書の場合は送る相手が多数なため手書きのように相手の名前が文中に入れられません。 フォーマル文では、活字(教科書体)が広く普及し使われています。 デジタル文字であれば、楷書体を使用し、楷書体をベースにして作られた教科書体を使用します。 セミフォーマル文も同じく手書きが好ましく、 文字書体はフォーマルを基準に様々な書体を使用してデザインするのも個性的でよい。
■ 文字レイアウトの基本知識
団体名や組織名(株式会社、有限会社、社団法人など)の商号に用いられる会社種別は頭に種別がくる場合と 後に種別がくる場合とでは文字の大きさが異なる。
例:
1. 株式会社 石井文庫(2~3ポイント小さい)
2. 石井文庫株式会社(同一ポイント)
3. 結語は1文字~半角、本文下の行より上げる
4. 日付は行頭から2文字の行頭から下げる
5. 差出人名は結語と下端をそろえる
6. 宛名は敬意を示すという意味で、差出人より上にする。行頭から1文字下げる
7. 日時、場所、会費などは行頭をベースに本文、宛名よりバランスに応じて下げる
8. その他レイアウト方式は各文例を参照
■ はがきと封書の使い分け方
冠婚葬祭における儀礼的な場合は封筒を用います。 恩恵に預かった方や上司など目上の人に対しても封書を用いた方が丁寧です。 詫び状、礼状、依頼状、人に頼む場合は、気持ちを込めて封書として礼を尽くします。 事務的な連絡通知、親しい人たちへの案内状や礼状は、ハガキの方がフランクでよい。
■ 往復はがき(送る側)
| ・ | 往復葉書は返事をあてにし、出席確認に使うものですから、目的、日時、場所、会費、 返信締め切り期限、会の名称、連絡責任者名、電話番号などを明確にする。 |
| ・ | 信用の葉書の表には必ず返送先の郵便番号、住所、姓名または会の名称を書き、
姓名(会の名称)の下の左寄りに、敬称のかわりに「行」「宛」の字を やや小さめに 添える。 |
■ 往復はがき(返事を出す側)
| ・ | 返信用の裏面には、御出席、御欠席、御住所、芳名などと敬語を使うのが礼儀です。 |
| ・ | 返信を出す場合は、まず表のあて名の下の「行」や「宛」の字を2本線を引いて消し、“様”の敬称を書きます。 官庁・学校・団体・会社・会などの場合は“御中”と書きます。 |
| ・ | 裏面の御出席、御欠席、御住所、芳名などの敬語「御」「芳」は必ず線を引いて消すのが先方に対する一般的な礼儀です。 また、たとえば出席の場合、「御」を消すだけでなく、「出席」の後に続けて「出席いたします」と書き添えたり、 会合ならば世話人、責任者へ何か一言書き添えると一層心のこもった気持ちが相手に伝わるでしょう。 欠席の場合も同様に、欠席理由やお詫びを一言添えるのが礼儀で、相手にその気持ちが伝わります。 |
| ・ | 返信はほとんど締めきり日がありますから、締め切り日に間に合うよう、 早めに出し先方の段取りに迷惑をかけないようにしましょう。 |